
 高齢や病気で判断能力が衰えた人の財産を管理する必要があるがどうしたらいいのか 高齢や病気で判断能力が衰えた人の財産を管理する必要があるがどうしたらいいのか
 不動産を売却したいのだが、その不動産の所有者または共有者の一人に判断能力がないのでどうすればいいか? 不動産を売却したいのだが、その不動産の所有者または共有者の一人に判断能力がないのでどうすればいいか?
 相続が発生したので遺産分割協議をしたいが、相続人の中に認知症になり、判断能力のない者がいる。 相続が発生したので遺産分割協議をしたいが、相続人の中に認知症になり、判断能力のない者がいる。
 将来自分が高齢や病気になったときに備えて、予め財産を管理してくれる人やその財産等の管理内容を決めておきたい。 将来自分が高齢や病気になったときに備えて、予め財産を管理してくれる人やその財産等の管理内容を決めておきたい。
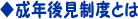
認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分になり、
不動産や預貯金などの財産の管理を行うことが困難となってしまう場合があります。
自分に不利益な契約であっても内容を判断することができずに契約してしまい、不当に財産を喪失したり、
それに伴い、生活資金に困るような状況を招く恐れのある人を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類に分類されます。
【法定後見制度】
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人(後見人・保佐人・補助人)が
本人の意思を尊重し、且つ本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、
本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりして、
本人を保護・支援する制度です。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類の制度があります。
【任意後見制度】
本人に充分な判断能力があるうちに、将来自分の判断能力が不十分な状態になることに備え、
予め自分が選んだ代理人である任意後見人に、自分の生活や療養看護、財産管理について、
その任意後見人に代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で作成するものです。
そして、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約によてい定められた業務を行い、
また家庭裁判所が選任する後見監督人の監督により後見人の業務を監督させて本人の意思に従った
保護・支援を行う制度です。
選任された成年後見人等は不動産や預貯金等の財産の管理、介護サービスや施設への入所などの契約手続などの
法律行為について支援を行います。
司法書士は成年後見の申立て手続を業務としております。
また、司法書士を成年後見人等に選任されるケースも多数ございます。
|

高齢や病気で判断能力が衰えた人の財産を管理する必要があるがどうしたらいいのか
不動産を売却したいのだが、その不動産の所有者または共有者の一人に判断能力がないのでどうすればいいか?
相続が発生したので遺産分割協議をしたいが、相続人の中に認知症になり、判断能力のない者がいる。
将来自分が高齢や病気になったときに備えて、予め財産を管理してくれる人やその財産等の管理内容を決めておきたい。
